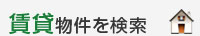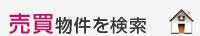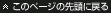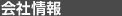相続登記とは?しないとどうなる?
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、不動産の相続が発生した際に行う手続きです。正式には「相続による所有権移転の登記」といいます。
具体的には、不動産の所有者(被相続人)が亡くなった際、その所有権を相続人に移す(書き換える)、つまり名義人を変更することです。
実はこの相続登記をはじめ、不動産所有権に関する登記は、法律で義務化されていませんでした。しかし不動産が売買されることによって所有者が変わったときには、ほとんどの場合所有者移転登記がなされます。にもかかわらず、相続登記に関しては放置されることが多かったというのが、これまでの状態でした。
相続登記をしないと罰金の対象に?相続放棄した場合はどうなる?
相続・遺贈による不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしないと、10万円以下の過料の対象になります。また、住所や氏名の変更をした場合、変更の日から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象になります。
このように、決して安くはない金額を負担しなければならなくなる可能性があるため注意が必要です。
他にも、手続きを放棄したことにより相続人の数が増えると、権利が複雑になっていきます。その結果、相続人全員での合意が困難になるというリスクが発生します。さらに、実際の所有者と登記簿上の所有者が違うと、正確な所有者がわからないため、土地の売却といった不動産投資や担保提供等の手続きを進めることが出来ません。
ちなみに、相続放棄をした場合は、相続人ではなくなるため相続登記義務化の規定は適用されません。 ただし、相続放棄は家庭裁判所に申請を行う必要があります。 また、相続放棄には期限があり相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内に行う必要があります。
「費用がかかるから」「手続きが面倒だから」といった理由で相続登記をせずに放置していると、さらにコストがかかったり、複雑な手順を踏むことになる可能性があります。そのため、余裕を持った早めの行動をおすすめします。
相続登記義務化の背景
前述したように、不動産に関する所有権の登記は法的義務がなかったため、相続しても使い道がない土地や空き家、そもそも相続人があいまいなままになってしまっている不動産は、相続登記がされることなく放置されることが多かったです。
その結果、現在国内には膨大な面積の「所有者不明不動産」があります。
相続が発生する段階になっても相続人があいまいなまま登記もされず、その結果本来相続した人からさらに相続人が発生し、どんどん相続人が増えていって、本来の土地の所有者がわからなくなってしまった、という土地が大量に発生してしまったのです。
相続登記が義務でなかった以上、当面の間は登記しなくても困ることはありませんでした。そうして所有者不明になってしまった土地が増加していくことで、いざ公共事業や再開発の際に所有者に連絡が取れない、手続きに時間や費用が莫大にかかる、というデメリットにつながっていったのです。
さらに、固定資産税の徴収も登記をもとに行われます。相続はしているのに登記しているか未登記かで固定資産税の納税のある・なしが発生するという、土地所有者の間で不公平が生まれてしまっていることも問題でした。
このような状態を背景に、国は相続登記の義務化を検討し、2024年4月から順次法律の改正が行われることとなったのです。
相続登記義務化の内容
相続登記の申請は3年以内に
相続が発生し相続人が決まった時点・自分が相続人であることを知った時点から「3年以内に相続登記をする」ということが、まず義務となります。
遺産分割で所有権を得た場合には、分割が決定してから3年以内に登記を行わなければなりません。
たとえ使い道がない不動産でも、相続登記の義務は生じます。先ほど述べた通り、正当な理由がなく登記を怠った場合には、最大10万円の過料が科されることがあります。
この義務化スタートは2024年4月ですが、施行になったらそれ以前に発生していた相続に関しても同様に登記の義務が生じるところに、注意が必要です。
登記名義人の住所変更などは2年以内
さらに、登記名義人、つまり所有権を持つ名義人の住所や氏名・名称に変更がある場合には、変更から2年以内に変更申請しなければならなくなりました。
名義人が転居などを何度も繰り返して、どこにいるのか所在がわからなくなってしまうことを防ぐために、こちらも義務化されました。
先ほど述べた通り、違反すると、5万円以内の過料が科されることがあります。
相続人申告登記制度の制定
遺産分割協議が長引いている場合の「救済措置」として、相続人申告登記制度というものも新設されました。
これは、相続人のうち誰がどの不動産を相続するかなどの具体的な内容が決まってないことが理由で相続登記ができない場合に利用できるものです。
相続人となる人が住所・氏名などの必要情報の届出さえあらかじめしておけば、相続開始から3年以上経過しても過料の対象とはなりません。
ただし、いうまでもなくこれは相続登記そのものではありません。「相続人が判明していること」を届出することで、一時的に相続登記の義務を果たしたとみなされるわけですが、あくまで「元の所有者が亡くなった」ということを示すに過ぎないのです。
そのため、遺産分割協議がまとまって相続人と相続内容が決まったら、改めて名義変更登記はきちんと行う必要があります。
「相続登記義務化」の問題点とポイント
遺産相続の分割協議期間は10年が限度となる
相続登記が行われないのは、相続人の間で遺産分割協議がなかなか進まず、相続内容の詳細が決まらないから、ということが理由になるケースも多々あります。
分割協議が継続している間は相続登記もなされないため、協議が長引くことで相続人が亡くなってしまい、さらに新たな相続人が生まれ…と事態がどんどんややこしくなるという事例もよく見かけました。
このような事態を防ぐために、「遺産相続の分割協議期間は10年間を限度とする」という内容も、今回の改正に盛り込まれました。
10年経っても遺産分割協議がまとまらない場合は、「法定相続に従った割合で分割する」ことになったのです。
10年とは長いようですが、協議がこれだけ長引いてもまとまらない事例が多くあったからこそ、今回このような制度が定められたわけです。
もし法定相続通りの割合ではない分割を望んでいる相続人がいる場合は、特に協議を急ぐ必要があるといえます。
「相続土地国庫帰属法」で国に引き取ってもらうことが可能に
相続したはいいけれど、自分で住むこともできず売却することもできない、使い道のめどの立たない不要な土地を、国に引き取ってもらって公共用地に転用されるという制度です。
不要な土地を所有し続けることの負担が大きく、手放したいけれど、そう簡単に売却できない事情がある人にとっての救済措置ともいえるものです。
資産価値に乏しい土地は、相続して登記をしても固定資産税がかかるだけだからと、登記のみならず相続自体にも消極的という人が多かったはずなので、そのような人にとってもありがたい制度といえるでしょう。
しかし、どんな土地でも対象となるわけではなく、要件がいくつも存在します。
まず、建物がある土地は引き取ってもらえません。解体して更地にする必要があります。
担保権や使用・収益を目的とする権利が設定されている土地も対象外です。
特定有害物質に汚染されている土地、境界線が明らかでない土地といったものも不可能となっています。
また、要件を満たして所有権を放棄しても、10年分の管理費用を国に支払わらなければなりません。
「相続登記義務化」に注意しよう!
これまでは「不動産所有権に関する登記には、法的な義務がなかった」ということを意外に思われた方も多いかもしれませんね。
この点がもっと早くから法律で義務化されていれば、、現在の「所有者不明な土地の大量発生」という問題は生まれていなかった可能性があります。今回の法改正により、相続登記について多くの不動産所有者の意識が高まり、問題解決につながっていくことが望まれますね。